「読書が大切なのはわかっているのに、なかなか続かない…」
そんなふうに感じている方は、実はとても多いのではないでしょうか。
仕事や家庭に追われる毎日の中で、「本を読む習慣をつけるにはどうしたらいいの?」「読書する余裕なんてないよ」と思ってしまうのは、大人ならではの悩みかもしれません。
でも実は、心や思考を整える“読書の時間”は、忙しい大人にこそ必要なもの。
この記事では、「読書習慣を身につけたい」と願うあなたへ向けて、本を読むことのメリット・デメリット7選をわかりやすくまとめ、その効果や向き合い方を徹底解説していきます。
本は、知識だけでなく、気持ちにもそっと寄り添ってくれる存在です。
小さな工夫から、あなたにぴったりの読書習慣を見つけてみませんか?
本を読む習慣をつけるには?大人にこそ必要な7つのメリット

以下でご紹介する各メリットは、著者自身の体験をもとにしていますが、読書の変化は読む本の種類やその方のもともとの性格・関心によっても異なる場合があります。
たとえば、小説を読むことで得られる想像力と、専門書から得られる知識や論理的思考力では、その質や深まり方に違いがあります。
「前向きになれる」「自分と向き合える」といった感覚も、内省的なテーマを扱った本など、内容によってより強く感じられることが多いでしょう。
その前提のうえで、私自身が感じた「大人の読書がもたらしてくれた変化」を、7つの視点からご紹介していきますね。
① 思考力が高まる(自分と向き合える時間)
本を読む時間って、ただ知識を得るだけじゃなくて、自分の考えを整理するチャンスでもあるんです。たとえば、内省的なエッセイや人生を見つめ直すような小説を読むと、自然と自分の気持ちを振り返るきっかけになります。
私も毎晩、寝る前にそういった本を少しだけ読むようにしたところ、気持ちが落ち着き、自分自身をやさしく見つめ直せるようになりました。
もちろん、一般的にこうした変化が期待されるとはいえ、読む本の内容やそのときの心の状態によっても、感じ方には違いがあるかもしれません。
② 集中力が高まる
スマホやSNSで、つい気が散ってしまう毎日。そんなときこそ、本を読む時間が心のトレーニングになります。
特に、物語の流れを追う必要がある小説や、少し難しめのビジネス書などを読むと、自然と集中する時間が長くなっていきます。
私自身、読書を習慣にしてから「人の話に最後まで集中できるようになった」と感じていますが、これは一般的にもよく言われている変化です。
ただし、読書の種類や個人の状態によって変化の感じ方には差があるかもしれませんね。
「読みたいのに集中できない…」という方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
👉 読書に集中できない?初心者でも集中力が続く7つの方法で読書がはかどる!
③ 言葉の力が自然と身につく
語彙力や表現力がついてくると、メールを書くときや人と話すときに言葉がスムーズに出てきます。
たとえば、エッセイや文学作品など、豊かな言葉づかいがされている本を読むことで、自然と語彙が増えていくことが多いです。
お仕事の文章も以前よりずっとラクになりましたよ。こうした変化は一般的に見られますが、どんな本を読むかによっても、身につく言葉の種類や表現の幅は変わってくると思います。
④ ストレスがやわらぎ、気持ちが落ち着く
「1日30分読書を続けるとどんな変化があるの?」という疑問に対して、私が実感したのは“癒し”の変化です。
特に、心が穏やかになるようなエッセイや、感情に寄り添ってくれる小説を読むと、リラックスできてストレスも軽減されやすいと感じます。
夜にお気に入りの本を読むと、心が静まり、ぐっすり眠れるようになりました。もちろん、どんな本を選ぶかによって、その癒しの度合いも変わってくるかもしれませんね。
なぜ読書がストレス解消につながるのか、もっと知りたい方はこちらもぜひ。
👉 読書がストレス解消につながるのはなぜ?読書習慣のメカニズムを検証
⑤ 想像力が育まれる
物語を読むことで、人の気持ちに寄り添う力や、知らない世界を想像する楽しさが広がります。
たとえば、ファンタジーや歴史小説のように、現実とは異なる世界を描いた本を読むと、想像力がぐっと広がっていく感覚があります。
読書って、まるで心の旅のようですね。
一般的にも、読書は想像力のトレーニングになると言われていますが、その変化の出方は読むジャンルや個人の感受性によっても異なるかもしれません。
⑥ 学びを実生活に活かせるようになる
「読書量が多い人の特徴って?」と聞かれたら、私は「学んだことを自分の言葉や行動に変えられる人」と答えます。
特に、ビジネス書や自己啓発本、実用書などは、得た知識をすぐに試してみたくなるような具体的なヒントが多いですよね。
本から得たヒントを、仕事や人間関係にうまく使えるようになりますよね。
ただし、得られる学びの深さや応用のしやすさは、読む本のジャンルや内容によって変わってくると感じています。
読書をしている人の“雰囲気”ってあるんですよね。その特徴については、こちらで詳しく紹介しています。
👉 本を読んでる人は顔つきでわかる?読書量が多い人の特徴や雰囲気も
⑦ 前向きな気持ちになれる
本を読むと、自分と向き合える静かな時間が生まれます。そこから少しずつ「こんなふうにしてみようかな」と前向きな気持ちがわいてくるんです。
特に、生き方に関するエッセイや、自分を励ましてくれるような言葉が並ぶ本は、気持ちをそっと支えてくれます。
一般的に、こうした読書体験は心を前向きに整えるとされていますが、その影響の大きさは読書の内容や、読むタイミングなどによって変わるかもしれませんね。
本を読む習慣をつけることは、大人の毎日を豊かに整えてくれる大切な習慣。
年齢を重ねた今だからこそ、読書がくれる“静かな変化”を味わってみてほしいなと、心から思います。
本を読むデメリットとは?紙の本・電子書籍・Audibleの違いも
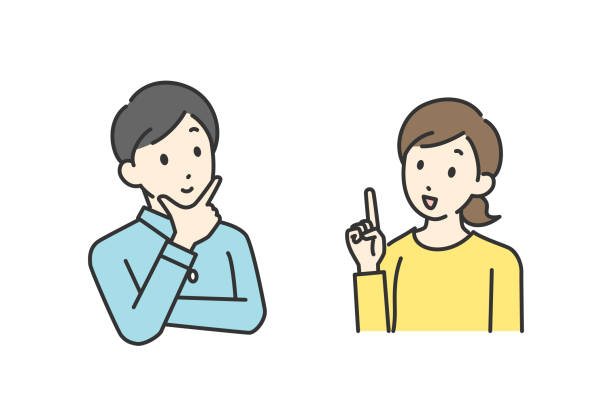
「本を読むメリットって何ですか?」という質問をよく見かけますが、実は「デメリットはありますか?」という声も意外と多いんです。
【読書における主なデメリット比較表】
| 種類 | デメリット | 補足・注意点 |
| 読書全般 | ・まとまった時間の確保が必要 ・本の内容が合わないとストレスになる | 読書習慣を始めるうえでの一般的なハードル |
| 紙の本 | ・重くて持ち運びにくい ・かさばる、保管場所に困る | 「手ざわりがよい」「記憶に残りやすい」といった魅力もあるが、不便に感じることもある |
| 電子書籍 | ・目が疲れやすい ・画面の見やすさに個人差がある ・プラットフォーム依存がある | 手軽で便利な反面、操作性や所有感に課題を感じる場合も |
こうしたデメリットを感じたときには、図書館で気になる本を借りてみたり、中古本を活用することで経済的な負担を軽減する方法もあります。
どちらが正解、ということではなく、「自分に合う方法で読書を楽しむ」ことがなによりも大切です。
最近では、電子書籍やAudible(音声読書)といった選択肢も広がっています。
電子書籍なら、スマホやタブレットがあればすぐ読めて、通勤中やちょっとした待ち時間にもぴったり。Audibleのような音声サービスは、目を休めたいときや家事をしながらでも“聴く読書”ができて便利です。
初めての方には無料体験もあるので、気になる方はこちらの記事もどうぞ。
👉 Audible完全ガイド!無料体験の期限、解約方法、メリット・デメリットを徹底解説
「紙の本じゃないと読んだ気がしない」と思っていた私も、いまでは気分やシーンに合わせて使い分けるようになりました。そのときどきの生活スタイルに合った方法で、無理なく読書を楽しめたら、それがいちばんですよね。
専用端末のKindleリーダーも気になる方は、モデルごとの違いをチェックしてみてくださいね。
👉 Kindle電子書籍リーダーの種類は?Kindle Paperwhiteの世代を比較してみた
ちなみに、KindleやAudibleには無料体験キャンペーンがあることも多いので、気軽に登録して試すことができます。いろいろな方法を試してみて、自分にぴったりの読書スタイルを見つけてみてくださいね。
実際に使ってみた人の声も気になるという方にはこちらを。
👉 Kindle Unlimitedの口コミやメリット・デメリットと使ってみた感想も
Kindle Unlimitedってどうやって登録するの?と気になった方には、こちらの記事がおすすめです。
👉 Amazon Kindle Unlimited の登録方法と料金プラン!解約方法もご紹介
本を読む習慣をつけるには?大人にこそ必要な、やさしい3つの工夫

「読書を習慣にしたい」と思いながらも、なかなか続かない…。
そんな悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。
とくに大人になると忙しさや気持ちの余裕のなさで、本を開く時間がつい後回しになってしまいますよね。
でも、本を読む習慣をつけるには、ちょっとしたコツと気の持ちようで、ぐっと続けやすくなるものなんです。
今回は、私自身が試して「これは無理なく続けられたな」と感じた3つの工夫をご紹介しますね。
それぞれの工夫には、心理学や行動習慣のヒントも込められています。大人にこそ必要な“心と知のリフレッシュ”、いっしょに始めてみませんか。
①「時間を見つける」のではなく「つくる」
「読書の時間がない」と思っていた頃、朝のほんの15分や、通勤前にカフェで過ごすひとときを読書にあててみたんです。
すると、本を読むことが自然と生活の一部になっていきました。
この「小さく始める」方法は、心理的ハードルを下げる工夫としても効果的なんです。
時間やエネルギーをかけすぎないと思えると、取りかかりやすくなり、ちいさな達成感が積み重なっていきます。
② 内容よりも「ページ数や時間」にフォーカスする
「今日は5ページだけ」「次の駅まで読んでみよう」。
そんなふうに“読む量”を決めると、不思議と気軽に本を開けるようになります。
内容の難しさにこだわらず、読む量を小さく区切ることで、心理的な負担が軽くなるんですね。
これは、読書を習慣化するうえでとても大切な視点なんです。
③ 最後まで読まなくてもいい、と自分にOKを出す
以前は「せっかく買ったから最後まで読まないと…」と、合わない本にも無理して向き合っていました。
でも今は、「ちょっと違うな」と思ったら、途中でそっと閉じてもいいと、自分に許可を出しています。
完璧を求めすぎないことも、大人の読書習慣には大切なコツです。
心の余裕を保つことで、読書に対する抵抗感が減り、むしろ自然と本に手が伸びるようになりますよ。
ちなみに、「途中で読むのをやめてもいいのかな…」と悩んだときにおすすめなのがこちらの記事です。
👉 本は最後まで読むべきか?途中でやめる判断基準とメリットや読まなかった本の活用法
本を読む習慣をつけるには、まず「読書はがんばらなくていい」と自分にやさしくすることが、いちばんの近道かもしれませんね。
まとめ
読書は、大人にこそ必要な“心の習慣”。
本を読む習慣をつけることで、知識だけでなく、自分自身と向き合う時間や、社会を理解する視野も広がっていきます。
小説では他者への想像力が、ノンフィクションでは背景への理解が深まるなど、そのメリット・デメリット7選を徹底解説した今回の記事。
忙しい毎日でも、1日5分から始めるだけで、きっと読書があなたの心の支えになってくれますよ!


