大阪万博の未来って、どんなふうに来るんだろう?
2025年4月13日から始まった大阪万博。
その場所は大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲(ゆめしま)です。
この万博が掲げるテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。
その言葉に触れたとき、私はふとこう思いました。
「未来って、どんなふうにやってくるんだろう?」
テクノロジーやAI、環境、共生…。
希望と不安が入り混じる「未来」という言葉に、そっと光を当ててくれるのが、本のなかの“近未来SF小説”たちでした。
今回は、大阪万博2025のテーマや場所に寄り添いながら、未来を考えるヒントになるような、やさしく心に届く近未来SF小説のおすすめ8選をご紹介します。
この記事は、「大阪関西万博をもっと深く楽しむための読書シリーズ」のひとつなんです。
海外文学やSF小説、公式ガイドブック、岡本太郎の芸術、関西が舞台の小説まで──。
気になるテーマがあれば、ぜひ他の記事ものぞいてみてくださいね。👉 シリーズまとめはこちら|大阪関西万博×読書シリーズ総まとめ
大阪万博2025のテーマと場所から考える、未来は「想像」から「行動」へ
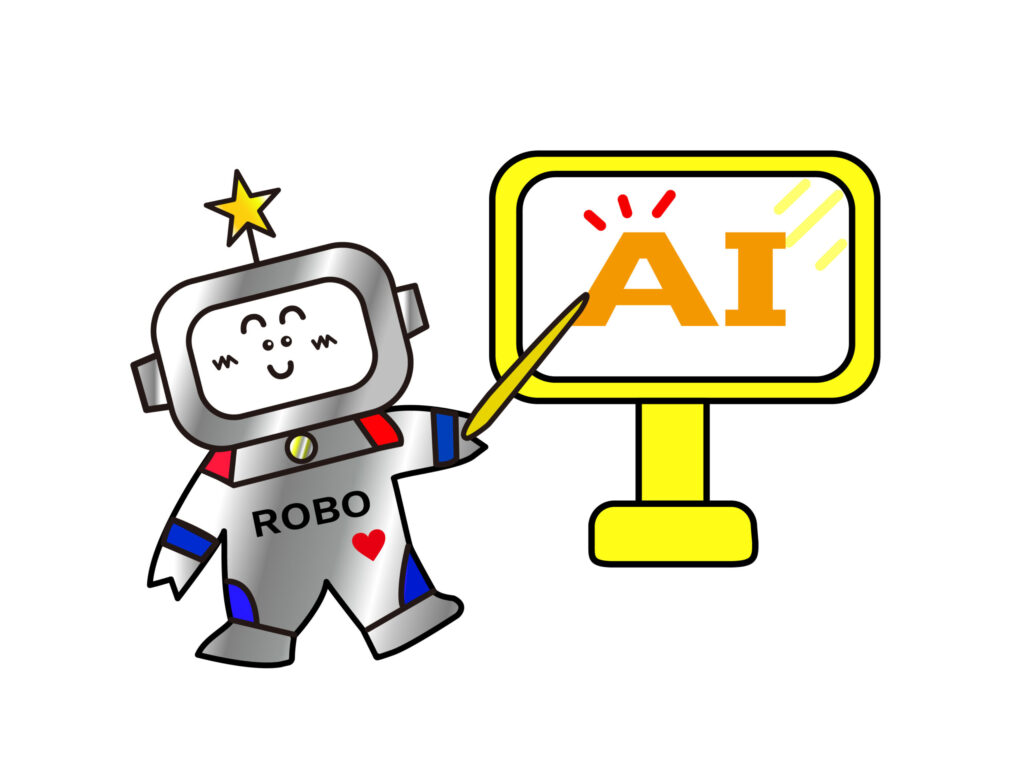
未来を想像すること──それはただ夢を描くだけではありません。
「こんな未来になったらいいな」
「こんな社会は避けたい」
そんな気づきが、少しずつ私たちの意識を変えていきます。
そしてその変化が、日々の行動や選択にもあらわれてくる。
未来を想像することは、未来に近づける第一歩になるのです。
大阪万博2025が目指す未来社会もまた、誰かに任せるのではなく、私たち一人ひとりが形づくっていくもの。
その想像力を育ててくれるのが、近未来SF小説の魅力です。
大阪万博2025のテーマと場所から感じる、小説が教えてくれる未来のかたち
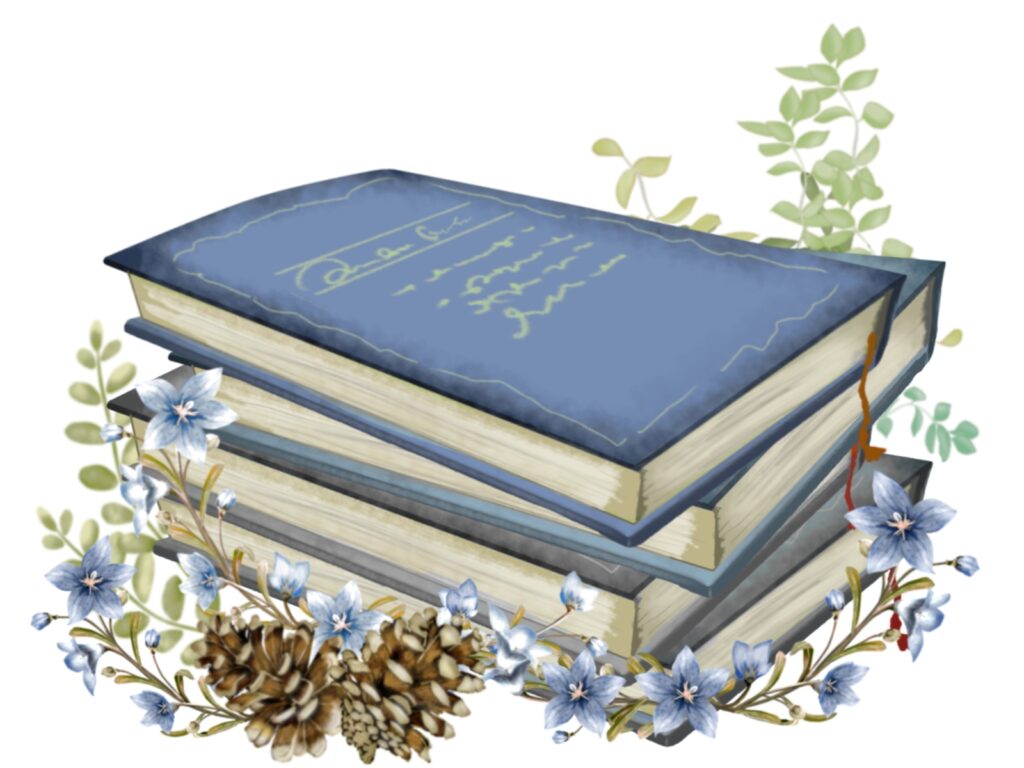
大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、多くのSF小説と共通する問いかけを含んでいます。
なぜ万博とSF小説が共鳴するのか、探ってみましょう。
大阪万博2025のテーマは、私たちの“暮らし”の延長にある
大阪万博2025のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」には、「多様性」「健康」「共生」といった、これからの未来を考えるうえで欠かせないキーワードが込められています。
たとえば、誰もが安心して医療を受けられる社会。違いを認め合い、支え合いながら生きていける共生のあり方。
そして、人と自然が調和して暮らす未来のかたち──。
そうした“やさしい未来”は、大阪万博の場所である夢洲で描かれようとしている社会像でもあり、実は多くの近未来SF小説のなかにも、そっと描かれているのです。
だからこそ、物語を読むことで「未来はこんなふうにも想像できるんだ」と気づくことができて、今の私たちの暮らしや選択にも、少しずつあたたかな視点が加わっていくような気がします。
近未来SFは難しそう? でも、実はとても“やさしい物語”です
SFと聞くと、なんだか難しそうで、専門的な世界が広がっていそう…そんなふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、実際の近未来SF小説はとても身近で、人の心のゆらぎや、家族や友人とのつながり、そして「これからの社会ってどうなっていくんだろう?」という、やさしい問いが描かれているんです。
少し先の未来を背景にしながらも、その物語の中心にあるのは、「もしあなたがその立場だったら?」という問いかけ。
だからこそ、未来にちょっぴり不安を感じている方にこそ、ぜひ読んでほしいジャンルなんです。
未来を想像することは、「今」を見つめ直すこと
未来について考えるということは、今の私たちの行動や選択が、これからの社会にどんな影響を与えるのかに気づくきっかけにもなります。
「未来ってどうなるんだろう?」と想像してみることが、「今、自分はどうしたい?どうありたい?」という問いへと自然につながっていくんですね。
そしてその問いは、より良い未来を築いていくためのやさしい道しるべになります。
たとえば、大阪万博2025の開催場所である夢洲では、AIや医療の進化、環境に配慮した暮らしなど、テクノロジーと人が共に生きる未来が描かれようとしています。
そうした未来像は、近未来SF小説に登場する“少し先の世界”ともどこか重なっていて、本を読みながら、「こんな未来を生きたいな」と思わせてくれる瞬間が、きっと訪れるはずです。
小説が教えてくれた、未来の輪郭
私にとって「未来を考える読書」の始まりは、 高校時代に読んだ『時をかける少女』でした。
時間を飛び越える少女の物語なのに、「今」をどう生きるかを問われているような感覚がありました。
それから、大人になって出会ったのが『ハーモニー』や『クララとお日さま』。 未来の医療管理社会、AIが生きる社会──。
どれも遠い話のようで、じつは日々の暮らしや価値観と深くつながっていて、 「私は、どんな未来を望んでいるんだろう?」と自然に考えるきっかけになりました。
大阪万博2025のテーマと場所から──近未来SF小説おすすめ8選
大阪万博2025のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」にぴったりな、少し先の未来を描いた近未来SF小説をご紹介します。
読書を通して、あなたの中にも“もうひとつの未来”が見えてくるかもしれません。
ハーモニー/伊藤計劃
大阪万博のテーマと対比するような視点を与えてくれる一冊です。
「健康でいることが“義務”になった世界で、あなたは自分の“心”や“体”を誰のものだと言えますか?」
『ハーモニー』は、パンデミック後の近未来を舞台にした近未来SF小説です。
舞台となるのは、すべての人がナノマシン「WatchMe」によって健康を監視される、完璧な健康社会。 病気や不調はすぐに対処され、人々は穏やかに暮らしています。でも、その“やさしさ”は、自由と引き換えだったのかもしれません。
そんな世界に違和感を抱いた少女・トァンたちが、自分の身体や心を“誰が支配しているのか”という問いに向き合いながら、選び取るべき生き方を模索していきます。
この本を読んで感じたこと、気づかされたことを、いくつか挙げてみますね:
- 健康や倫理が「正しさ」とされたとき、私たちはどこまで自由に生きられるのか?
- 「自分の体は本当に自分のもの?」と問い直したくなる場面がたくさんあります。
- SF小説なのに、社会や心のリアルが描かれていて、読後にふと現実を見つめ直してしまいます。
- 難しい技術ではなく、“考えること”が主役の物語なので、SF初心者さんにもおすすめです。
大阪万博2025のテーマや開催場所から未来社会を考えるとき、この一冊はまさに「考えるきっかけ」としておすすめです。
伊藤計劃さん(いとう けいかく)は1974年生まれのSF作家。2007年『虐殺器官』でデビューし、『ハーモニー』で高い評価を得る。2009年に34歳で逝去。短い活動期間ながら日本SF界に大きな影響を与えた。
クララとお日さま/カズオ・イシグロ
人とAIの共生がテーマとなる大阪万博2025に通じる感動作です。
「やさしさって、どこから生まれるんだろう?」 そんな問いかけに、静かに寄り添ってくれるのが『クララとお日さま』です。 舞台は、近未来。 人工知能のAF(人工親友)であるクララは、ショーウィンドウの中から世界を観察しています。
太陽の光を大切に感じながら、人間の心にそっと寄り添おうとする姿は、とても健気で、どこか人間以上に“心”を持っているようにさえ思えます。 やがてクララは、病弱な少女ジョジーのもとで暮らすことになります。ジョジーと彼女の家族、友人たちと過ごすなかで、クララは愛や絆、信じる力のかたちを学んでいきます。
- AIの視点から描かれる“やさしさ”が、心に静かに染みわたります。
- 「人間らしさ」とは何かを改めて考えるきっかけになります。
- 大阪万博の場所である夢洲の未来都市イメージにも通じる、静かで美しい近未来の描写です。
未来に少し不安を感じている今だからこそ、大阪万博2025のテーマにふさわしいこの近未来SF小説を、そっと開いてみてくださいね。
カズオ・イシグロさんは1954年長崎生まれ、5歳で渡英。英文学を学び、1982年に作家デビュー。『日の名残り』でブッカー賞、『わたしを離さないで』は映像化され、2017年にノーベル文学賞を受賞。現在はイギリス国籍を持つ世界的作家です。
時をかける少女/筒井康隆
時間を超える青春物語。
未来は遠い場所ではなく、「今」の延長線上にあることを教えてくれます。 大阪万博が描く「未来社会」とは、私たち一人ひとりの“今”の積み重ねかもしれません。
「もし昨日に戻れたら、あなたは何をやり直しますか?」
そんな気持ちに、やさしく寄り添ってくれる物語が『時をかける少女』です。
- 「当たり前の日常」がどれほど大切か、改めて実感できます。
- やり直したい気持ちと、それができない切なさに触れ、「今」を大切に生きたくなります。
- タイムリープという設定は、大阪万博2025の未来技術やテーマとも重なる想像力の入り口です。
「大阪万博のテーマを文学で味わう」そんな読書体験をしてみませんか?
筒井康隆さん(1934年大阪生まれ)は、ナンセンス文学やSF、メタフィクションなど多彩な作品で知られる作家。1960年に作家デビューし、『家族八景』『虚人たち』などの代表作を持つ。日本SF界の「御三家」の一人としても著名。
星を継ぐもの/ジェイムズ・P・ホーガン
科学と未来社会を結ぶ、大阪万博の「知」のパビリオンにふさわしい一冊です。
「宇宙の謎にワクワクしたい」そんな気持ちがふと湧いてきたときに、ぜひ手に取ってほしいのがこの一冊。
『星を継ぐもの』は、近未来の月面で発見された“チャーリー”という謎の遺体から物語が始まります。なんと、彼は5万年前に死亡していたにもかかわらず、明らかに“地球人ではない”のです。
この衝撃の発見をきっかけに、科学者たちは天文学・考古学・遺伝子学など、あらゆる知識を総動員して、チャーリーの正体と人類の起源、そして宇宙に隠された真実に迫っていきます。
月から地球、そして宇宙全体へとスケールが広がっていくこの物語は、論理的な謎解きと人間ドラマが巧みに絡み合った、まさに知的冒険の旅。
この本から感じたこと、得られた気づきは──
- 科学の力と人間の想像力、どちらも欠かせない大切なものだと気づかされます。
- 論理的に物事を考える面白さ、知的好奇心が満たされる満足感。
- 宇宙や人類の歴史に対して、新しい見方や驚きが生まれます。
- 「もしかしたら本当に…」と思えるほど、物語にリアリティと迫力があります。
大阪万博2025の開催地である夢洲が未来への扉を開く場所であるように、この近未来SF小説もまた、読者の知的好奇心と想像力を広げる「出発点」になるでしょう。
SFというよりも、謎解きミステリーとして楽しめる側面があり、難しい用語が出てきてもストーリーに自然と引き込まれていくので、SF初心者さんにもおすすめです。
もし少しでも「宇宙の謎」や「人類のルーツ」に心が動くなら── この物語は、あなたの知的冒険心をそっとくすぐりながら、遠く広がる未来へと誘ってくれるはずです。
ジェイムズ・P・ホーガンは1941年ロンドン生まれのSF作家。技術者として働いた後、『星を継ぐもの』で作家デビューし、日本で星雲賞を複数受賞。2010年、アイルランドの自宅で心不全のため69歳で死去した。
幻想の未来/筒井康隆
日常のすぐ先に広がる、ちょっと不思議で、どこか胸に残る“未来”のお話──。 『幻想の未来』は、ユーモアと社会風刺が効いた、筒井康隆さんによる近未来SF短編集です。
「もし、明日世界が変わったら、あなたはどう生きていきますか?」
そんな問いからはじまるこの物語たちは、まるで予言のように、私たちの心の奥にそっと問いかけてきます。
表題作では、核戦争や炭疽熱で荒れ果てた未来の都市が舞台。 でも、描かれているのは“終わり”ではなく、そこからの“再生”や“希望”。 人間の本能、そしてつながりが、静かに浮かび上がってくるような、そんな読後感が残ります。
この本がそっと届けてくれるもの:
- 「人間って、なに?」そんな根っこの問いにやさしく触れられる
- 極限の中でこそ見えてくる、希望や本能の力
- 恐ろしい未来を描くことで、いまの不安がすこし軽くなる
- 想像する力が、心の奥をふわっとやわらかくしてくれる
大阪万博2025の場所である夢洲(ゆめしま)では、「未来社会」や「生命のかたち」をテーマにした展示も予定されています。
この作品のように、ちょっとユニークな角度から未来を見つめることで、自分らしい未来のとらえ方に出会えるかもしれません。
SFが苦手な方にもおすすめしたい理由:
- 難しい科学の話よりも、人間模様や感情が中心
- 一話ごとに完結するので、少しずつ読めて気軽に楽しめる
- 重たすぎないけれど、再生や希望の光が感じられる
- 筒井さんらしい皮肉と笑いが、ちょっぴり効いています
未来にちょっと不安を感じたとき── この一冊が、あなたの想像力と生きる力をそっと後押ししてくれるかもしれません。
筒井康隆さん(1934年大阪生まれ)は、ナンセンス文学やSF、メタフィクションなど多彩な作品で知られる作家。1960年に作家デビューし、『家族八景』『虚人たち』などの代表作を持つ。日本SF界の「御三家」の一人としても著名。
タイタンの妖女/カート・ヴォネガット
地球と火星の戦争、運命論と自由意志──荒唐無稽でありながら深く哲学的な近未来SF。
「人生の意味がわからない」「自分の運命は誰かに操られている気がする」そんな不安や疑問を抱えたことはありませんか?
『タイタンの妖女』は、カート・ヴォネガットが描く壮大な近未来SF小説。
全米一の大富豪マラカイ・コンスタントが、謎めいた存在ラムファードに導かれ、地球から火星、水星、そして土星の衛星タイタンへと、時空を超えた運命の旅へと巻き込まれていきます。
ブラックユーモアと皮肉の効いた文体で描かれるのは、偶然と必然が交差する中で、人間の「自由意志」や「人生の意味」に迫る深い問いかけです。
この本が教えてくれること
- 「自分の人生は本当に自分のものなのか?」という問いに、ユーモアと哲学で寄り添える
- 宇宙の広がりの中で感じる、孤独と安心感の不思議な共存
- 人生の転機や偶然に意味を見出そうとする姿に共感できる
- 意味のなさや偶然を受け入れることで、肩の力がふっと抜ける
SFに苦手意識がある方にもおすすめの理由
- 難解な設定よりも、物語として楽しめる展開
- 解説では爆笑問題・太田光さんが「意味がわからなくても面白い」と紹介
- 「人生小説」としても読める心の深さがある
- 「もしかして、自分も誰かに操られている?」そんな共感の芽が生まれる作品です
「SFって難しそう」と思っている方にも、ぜひ手にとってほしい一冊。
物語の流れに身をゆだねながら、心の奥に静かに問いを投げかけてくれるような読書体験になるはずです。
カート・ヴォネガット(1922–2007)はアメリカの小説家。ドレスデン空爆の体験を基にした『スローターハウス5』など、風刺とユーモアを交えた近未来SFで知られる。戦後は文化人類学を学び、作家として現代文学に大きな影響を与えた。
生命式/村田沙耶香
「生きる」ことの価値をめぐる短編集。
常識にそっと問いを投げかける、未来型文学です。
「“普通”って、誰が決めるんだろう?」 そんなふうに感じたことはありませんか?
価値観が一夜で変わるようなこの時代、日常の“当たり前”にふと疑問を抱く瞬間は、きっと誰にでもあるはずです。
村田沙耶香さんの『生命式』は、そんな感覚にやさしく寄り添ってくれる一冊。 死者を食べて命をつなぐという「生命式」が常識になった近未来を舞台に、私たちの“普通”が問い直されていきます。
この本がそっと教えてくれること
- 「普通」や「常識」がいかに移ろいやすいものかに気づける
- 他者との価値観の違いに悩むことは、ごく自然なことだと感じられる
- 命・生・性といった根源的なテーマに向き合い、自分なりの“当たり前”を見直せる
SFが苦手な方にもやさしいポイント
- 現実の社会や人間関係の延長として描かれているので、物語に入りやすい
- 極端な設定だからこそ、現実の悩みにも不思議と寄り添ってくれる
- 短編集なので一編ずつ、好きなときに読める手軽さも魅力です
“普通”に違和感を覚えたことがあるあなたへ。
ちょっとだけ勇気を出して、『生命式』の世界をのぞいてみませんか?
きっと、あなた自身の“当たり前”が少し優しく、自由になるはずです。
村田沙耶香さん(むらたさやか)は1979年千葉県生まれの作家。2003年にデビューし、『コンビニ人間』で芥川賞受賞。ジェンダーや家族観など社会の「当たり前」を問い直す作風で、国内外で高く評価されている現代文学の旗手。
夏への扉/ロバート・A・ハインライン
失われた時間を取り戻す旅。
未来への扉を開くような希望と再生の物語です。
未来に希望を持ちたいあなたへ――裏切りや不安に傷ついた心も、「夏への扉」はきっと見つかる。
『夏への扉』は、天才発明家ダニエル(ダン)と愛猫ピートの絆を軸に、1970年から2000年へとタイムトラベルする近未来SFです。
信頼していた人たちに裏切られ、すべてを失ったダンは、冷凍睡眠から目覚めた未来で、もう一度人生の夏を取り戻すために立ち上がります。
ロボット技術やコールドスリープといった未来の要素を背景にしながらも、描かれているのは、希望、信頼、そして愛するものとの再会を信じる気持ち。
やさしさと勇気がじんわりと胸に残る、再生とハッピーエンドの物語です。
この本がそっと届けてくれるもの
- 困難の中でも、希望を持ち続けることの大切さ
- 技術よりも、人との絆が人生を豊かにしてくれるという気づき
- 未来は自分の手で切り開ける、という前向きなメッセージ
- 猫好きにはたまらない、ピートとの絆に心がほっこり温まる
- 読み終えたあと、静かに背中を押してくれるような爽やかさ
SFが苦手な方にもおすすめの理由
- 難しい用語よりも、人間の感情を丁寧に描いていて読みやすい
- 現代にも通じる発明や家電が登場し、未来を身近に感じられる
- 主人公の不器用さや誠実さに共感しやすく、心に寄り添う内容
- 猫とのやりとりや伏線の回収も楽しく、読書体験そのものが心地よい
もし今、少しでも未来に迷いや不安を感じているなら 、 『夏への扉』をそっと開いてみてください。 あなたの心にも、あたたかな季節の風が届くはずです。
ロバート・A・ハインライン(1907〜1988)はアメリカのSF作家で、「夏への扉」などの名作を生んだ近代SFの巨匠のひとり。海軍を退役後、理系の知識を生かして人間や社会を深く描く作品を数多く残しました。
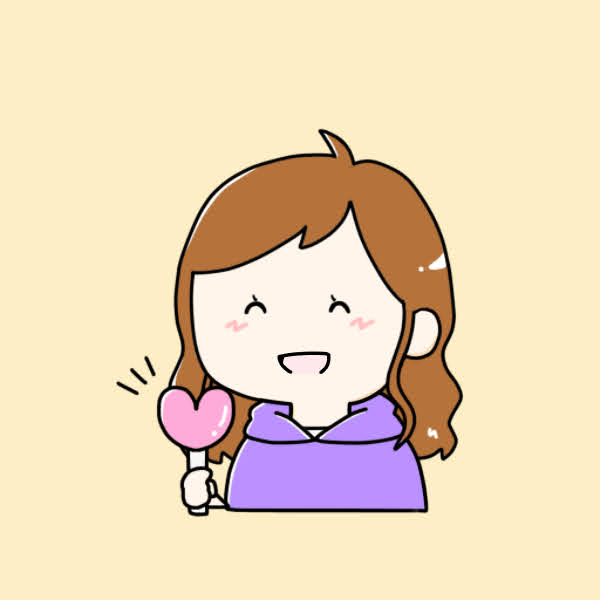
未来の物語を旅したあとは、ちょっと寄り道して、過去の大阪や人間くさい文学にも触れてみませんか?
未来の社会を描くSF小説を読んでいると、ふと、「昔の大阪」や「人間そのものの姿」にも目を向けたくなることがあります。
そんなときに読みたくなるのが、昭和の大阪を舞台に、人情とユーモア、そして哀しみを描いた織田作之助の作品たち。
人が人として生きる姿が、未来とは違う角度から胸に沁みます。
▶︎ 織田作之助のおすすめ作品10選と魅力的な作風を紹介!青空文庫での読み方もチェック
さらに、整った社会や“正しさ”に反発し、あえて弱さを描いた作家たち──無頼派の世界にも、未来社会とは対照的なまなざしがあります。
太宰治、坂口安吾とともに歩んだ織田作之助の背景を知ると、文学の広がりがぐっと深まりますよ。
▶︎ 織田作之助と無頼派とは?太宰治・坂口安吾との関係や意味を解説
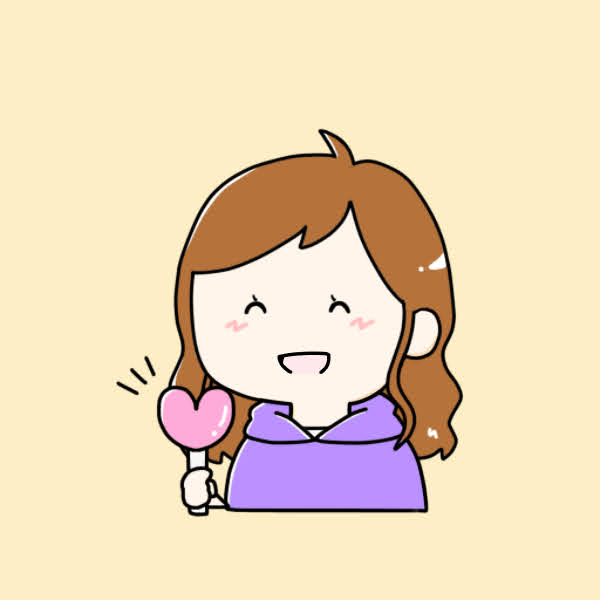
本はやっぱり軽くて、いつでも読めるほうがいいな」そんな方には、Kindle Unlimitedもおすすめですよ。スマホやタブレットがあれば、未来小説も気軽に楽しめます。

「目が疲れていて、でも本の世界には入りたい…」そんなときは、Audibleで“耳読書”という選択肢もあるんだ。
移動中や家事の合間にも、やさしく物語が寄り添ってくれるから心地よいよ。
今回ご紹介した未来小説は、紙の本はもちろん、電子書籍やオーディオブックでも楽しめます。
「紙より軽いほうがいいな」「目が疲れるから音で聴いてみたい」
そんなときは、Kindle UnlimitedやAudibleを使って、自分に合ったスタイルで読書を楽しんでみてくださいね。
▶︎はじめてでも大丈夫。やさしくまとめたガイドはこちらです♪
Amazon Kindle Unlimitedの使い方・料金・解約方法を徹底解説!初心者向けガイド
▶︎Audibleをはじめてみたい方へ。無料体験から使い方までご紹介♪
Amazonオーディブル完全マニュアル【2025年版】|無料体験期間・メリット・解約手順
万博が描いた未来は、終わっても私たちの想像の中で生き続けています。
それでも、ふと静けさを感じる夜に──
もう一度、“希望の物語”に触れてみませんか。
👉 大阪関西万博が終わって寂しい…“万博ロス”を癒す本と次に向かうヒント
大阪万博とともに未来を読む時間を まとめ
大阪万博2025の場所・夢洲には、世界中から集まる未来のアイデアが詰まっています。そして、本の中にもまた、無数の未来が描かれています。
未来は遠くの誰かのものではなく、私たち一人ひとりが描き、選び、歩んでいくもの。
近未来SF小説を通して、「こんな未来があったらいいな」と想像する時間が、きっと“いま”をやさしく照らしてくれますように。
「面白そう…でも、どれから読もう?」
そんなふうに迷っているあなたに、ぜひ声を大にして伝えたいんです。
まだ、読んでいないなんてもったいない。
どの記事からでも、きっと「これだ!」と思える出会いが待っています。
たとえば――
- 海外文学の世界から、大阪万博をもっと深く味わいたいなら
👉 大阪万博で読みたい本おすすめシリーズガイド|パビリオン×海外文学総まとめ
大阪関西万博の世界のパビリオンを、もっとたくさんの物語で旅してみませんか?気になる地域から、ぜひのぞいてみてくださいね。
ヨーロッパ中部・北欧編|Vol.1
ヨーロッパ西部・南部編|Vol.2
英語圏編|Vol.3
アジア・中南米編|Vol.4 - まずは全体をつかみたい、そんなあなたにぴったりのガイド本なら
👉 万博で人気の本6選【最新版】大阪・関西万博の公式ガイドブック&目的別入門書まとめ - 太陽の塔と岡本太郎、芸術の爆発を体感したくなったら
👉 大阪万博の太陽の塔はどんな場所に?岡本太郎の芸術と想像力が生まれた瞬間 - 「いのち」「共創」「未来社会」──万博の理念をもっと深く知りたくなったら
👉 大阪関西万博サブテーマを読書で体感?理念から考えるいのち・共創・未来社会と本 - 万博の舞台・関西を小説で旅するなら
👉 関西が舞台の小説まとめ|万博とともに読みたい、作家たちのまなざしで辿る土地と人生の物語
どれも、今だからこそ読んでほしいものばかりなんですよね。
気になったときが、読書のタイミング。
さあ、次の一冊へ。あなたの“気になる”を、ここから広げてみませんか?
▶ 未来を想像するワクワク感を味わったら、今度は大阪という「現実の街」にも注目してみませんか?過去から今、そして未来へとつながる大阪の物語をご紹介しています。👉 大阪を舞台にした小説まとめ|1970大阪万博から2025まで読み解く街と物語の魅力










