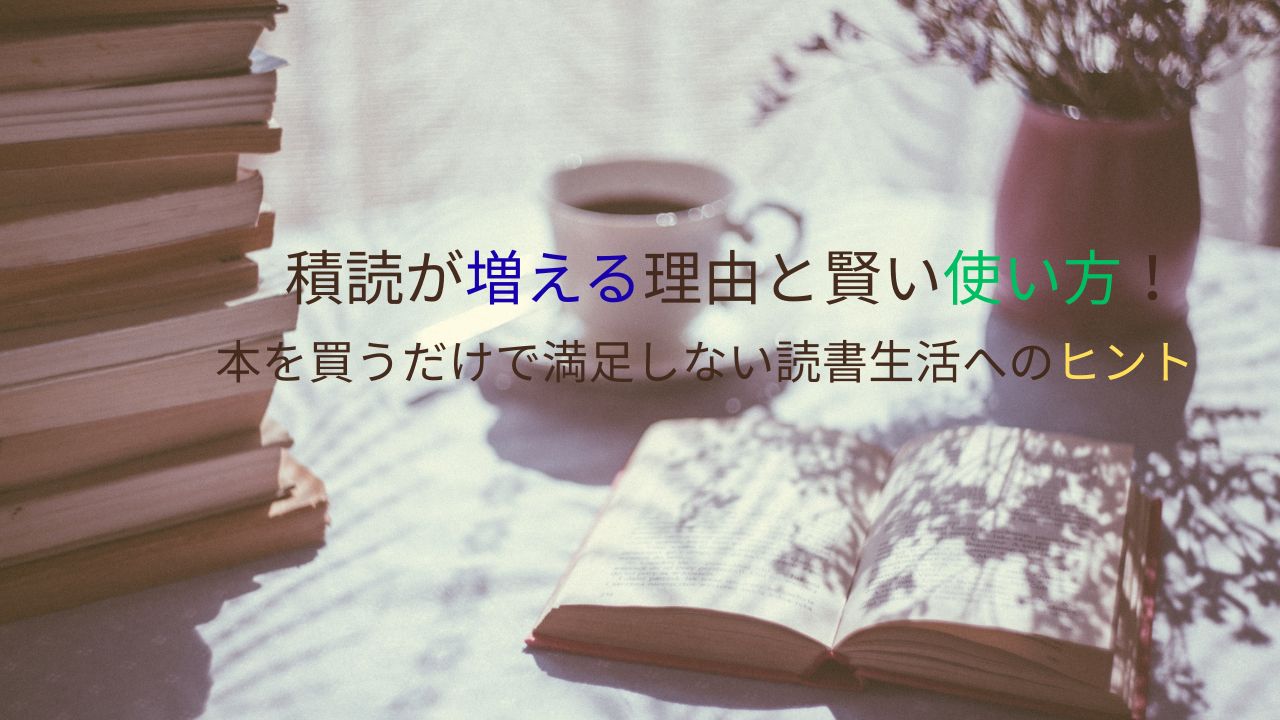「読みたい」と思って買ったはずなのに、気づけば読まずに積んだまま、積読が増える──そんな本、ありませんか?
実はその“積読”、多くの読書好きが抱える共通の悩みなんです。
でも、大丈夫。
この記事では、積読をただの「読まない本の山」として片付けず、心を豊かにする“味方”として増える本を活かす方法をご紹介していきますね。
積読が増える理由とは?

積読とは「本を買っても、すぐには読まずに積んでおくこと」。
忙しい毎日、時間が取れない…そんな理由で、読みたい気持ちがあっても、手を伸ばせないことってありますよね。
また、購入時は惹かれたのに、後から「難しそう」「今の気分じゃない」と感じて、なんとなく後回しにしてしまうことも。
さらに、電子書籍やAudibleの普及で、本を手に入れるハードルが下がった分、読みきれない本がたまりやすくなっているのも事実です。
でも、それって裏を返せば、「いつでも読みたい本が手元にある」という安心感の証でもあるんですよね。
📚読まずに本を積んでしまう…そんなあなたに。積読本は何冊あっても大丈夫!読みたくて買った本を積む理由と快適に楽しむコツ
📚本を選ぶときに「つい」手が伸びてしまう方へ。読まないのに本を買ってしまう|本好きが買いすぎを防ぐ7つの気づきと5つの選書法
積読を減らす具体的な対策法
積読の「理由」がわかれば、「対策」も見えてきます。積読を減らす具体的な対策法をご紹介しますね。
1. 忙しくて読む時間が取れないときは…
スキマ時間に読む・聴く工夫を
- 通勤中にKindleアプリで読書。
- 料理や洗濯中にAudibleで“ながら読書”。
「本を開く」時間が取れないなら、「耳で聴く」読書を取り入れてみましょう。
▶スキマ時間に“聴く読書”を始めたい方はAudibleの詳しい記事を参考にしてくださいね
Amazonオーディブル完全マニュアル【2025年版】|無料体験期間・メリット・解約手順
2. 本が難しそう・読む気が起きないときは…
気分に合った本を選び直す
- 短編集やエッセイなど、軽めのものから始める。
- 今の自分が読みやすそうだと感じる1冊を再セレクト。
関連:本がなぜか読めない…そんなときに読んでほしいヒントがあります。
小説が読めなくなった読書好きへ!その理由と読書の楽しみを取り戻す方法
3. 増える本に気後れしているときは…
積読は「読む順番」と「目につく場所」を工夫する
- 今週読む3冊だけを、ベッドサイドやリビングに置く。
- 本の表紙が目に入る場所に飾って、気持ちを引き寄せる。
積読を楽しむポジティブな考え方
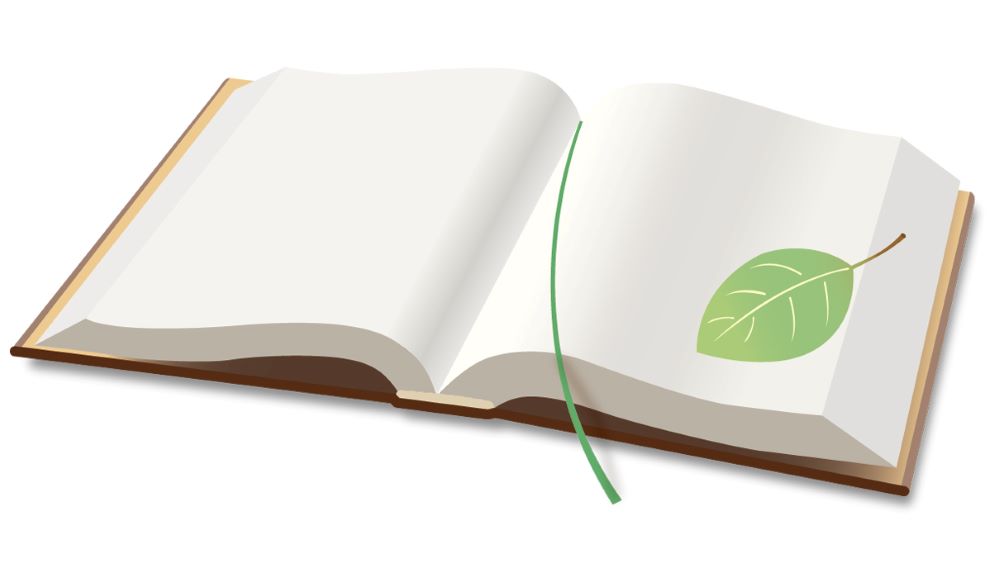
積読は、「未来の自分に残しておいたプレゼント」なんです。
たとえば、
- 今日はどれを読もうかと迷う時間
- 読まずにそっと積まれた背表紙を眺める時間
そんなひとときも、立派な“読書”の一部。
そして、手元にある増える本(積読)は「知識のストック」「心の避難所」。
読む準備ができたとき、すぐに扉を開けることができるんです。
読書SNSやアプリで積読リストを公開するのもおすすめ。
人とつながることで、積読に新しい意味が生まれるかもしれません。
積読解消に役立つ方法とツール
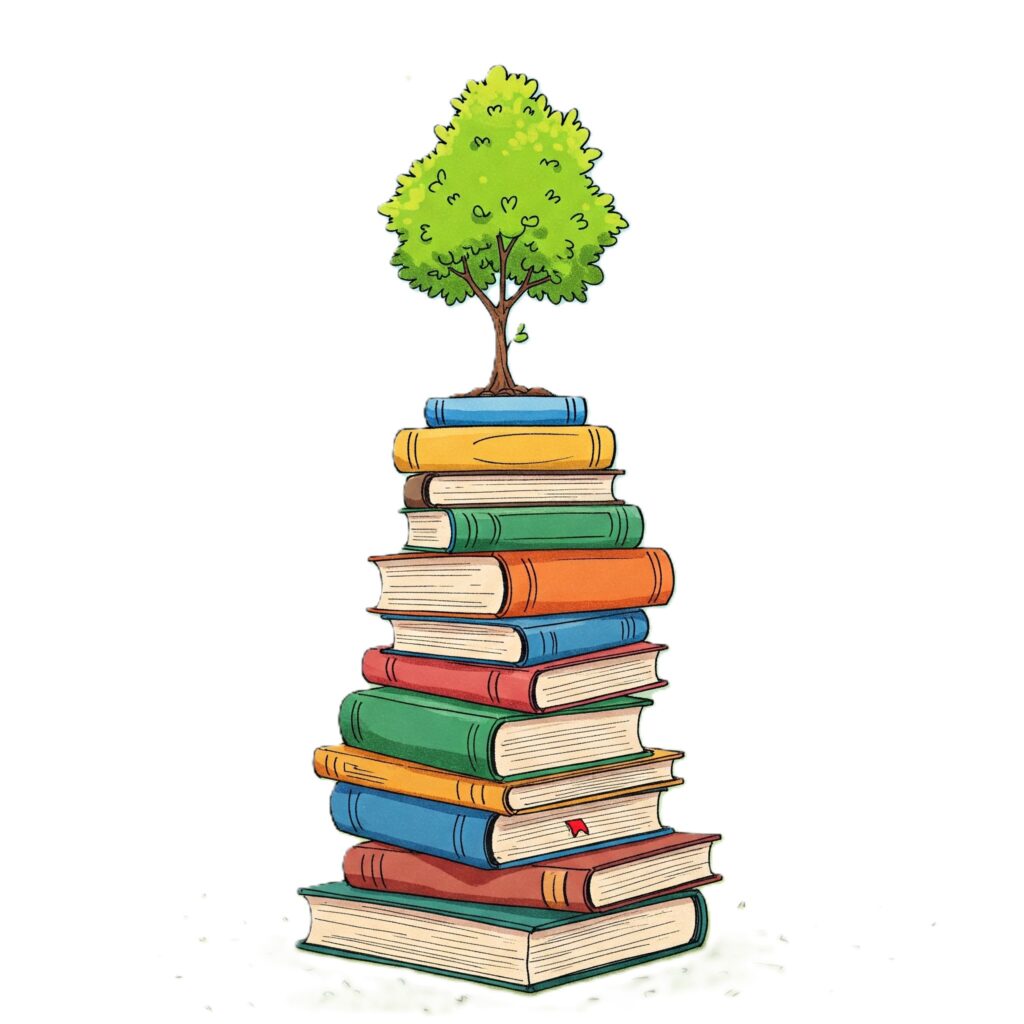
積読を減らすためには、日々のちょっとした工夫と便利なツールの活用が効果的です。
ここでは、手軽に試せる3つの方法をご紹介します。
1. 積読ノートやアプリで整理
積読本のタイトルや購入日、気になった理由を書き出してみると、自分の興味の傾向が見えてきます。
無料で使える読書記録アプリを活用すると、進捗が見える化されてやる気アップに!
2. 図書館の“返却期限”を利用する
「借りた本は読まなきゃ」という適度なプレッシャーで、読書習慣を自然と後押し。
気軽に試せて、読まなくても罪悪感が少ないのが図書館の魅力です。
3. 電子書籍・オーディオブックでスッキリ読書
KindleやAudibleを活用すれば、紙の本よりも場所を取らず、気軽に読書を始められます。
- Kindle Unlimited:月額制で200万冊以上が読み放題
→ Kindle初心者の方は、こちらで使い方から解約までしっかり確認できますよ。
Amazon Kindle Unlimitedの使い方・料金・解約方法を徹底解説!初心者向けガイド - Audible:耳で聴ける本が12万冊以上!
→ Audibleの魅力や使い方をもっと知りたい方はこちらをご覧ください。
Amazonオーディブル完全マニュアル【2025年版】|無料体験期間・メリット・解約手順
どちらも30日間の無料体験があるので、まずは試してみるのが一番です。
まとめ|積読を活かす読書スタイルへ
積読があるということは、「読みたいと思った瞬間」が、あなたの中にあったということ。
その気持ちを、どうか大切にしてくださいね。
本は、読むタイミングも、それぞれのペースも、自由でいいんです。
積読を責めるよりも、活かす工夫を。
そんなふうに日々の読書がちょっとずつ楽しくなっていったら、それが何よりの“読書の力”なんだと思うんです。
今日もあなたの本棚に、そっと寄り添う一冊がありますように。