この【パビリオン×海外文学】シリーズでは、万博で出会う世界の文化とつながる海外文学をご紹介しています。
Vol.3となる今回は、英語圏に注目してみました。
英国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アイルランド──時代を超えて愛され続けてきた名作たちが、私たちに大切なことを静かに、でもしっかりと教えてくれます。
今回ご紹介する書籍は、海外文学作品であり、日本語に翻訳されているものの中から、私たち日本人が読みやすい本を選び抜いています。
どの一冊も心に響くものばかりですので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
▶シリーズ全体のおすすめ本まとめはこちら
👉 大阪万博で読みたい本おすすめシリーズガイド|パビリオン×海外文学総まとめ
大阪万博のパビリオンで感じる英語圏の海外文学の魅力
英語圏の国々のパビリオンでは、テクノロジーや未来へのビジョンとともに、それぞれの文化が大切にしてきた「ものの見方」にも出会えます。
そんな深いまなざしにふれるには、その国で生まれた本──つまり海外文学を手に取ってみるのがおすすめです。
たとえば英国のユーモア、アメリカの挑戦心、カナダの自然観、アイルランドの詩情、オーストラリアの土地の記憶……。
万博の余韻とともに読むことで、物語がより鮮やかに感じられるはずです。
なぜ英語圏の本を読むのか?万博とのつながり
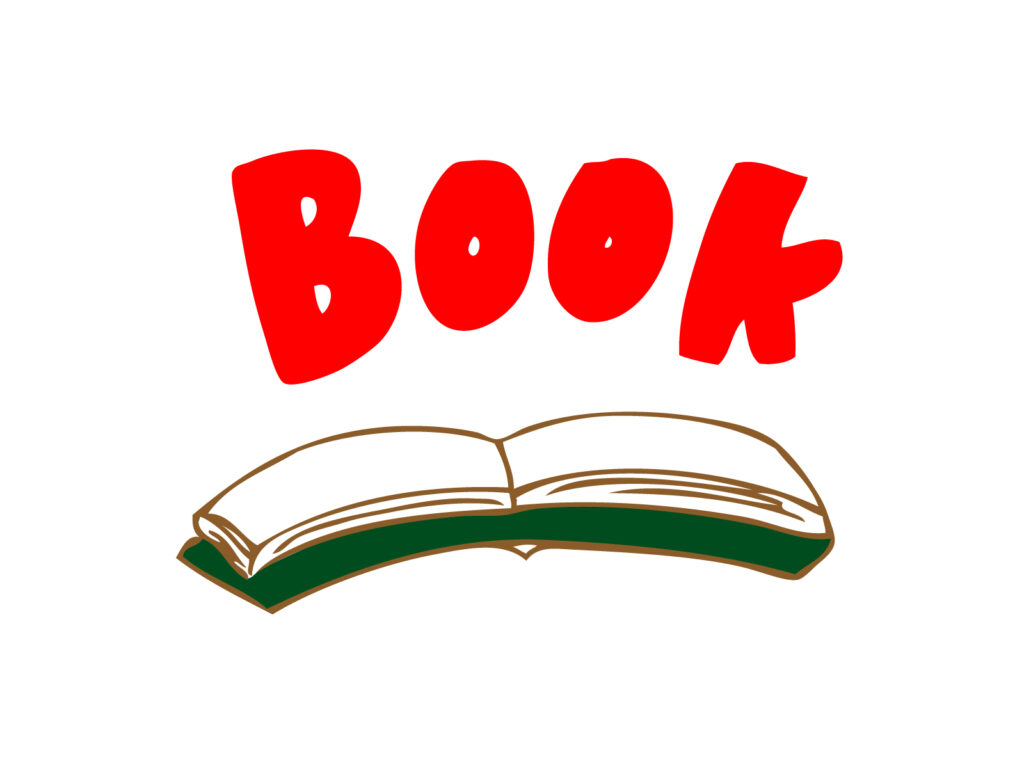
英語圏の海外文学には、私たちが日々感じる喜びや不安、希望といった感情が、とても繊細に、そしてリアルに描かれています。
大阪万博のテーマ「未来社会のデザイン」と重なるような、柔らかくもしなやかな視点が、多くの作品に込められています。
未来を語るとき、私たちは過去や今にもしっかりと目を向けていきたい。
だからこそ、英語圏の本は、万博と出会うこの瞬間にぴったりの一冊になるのかもしれません。
おすすめ本10選|英語圏のパビリオンとつながる海外文学
ここからは、英語圏の国々のパビリオンにちなんだ「海外文学」のおすすめ本をご紹介していきますね。
それぞれの物語には、その国で大切にされてきた価値観や暮らしの風景が、やさしく息づいています。
ご紹介する書籍は、海外文学の中でも日本語に翻訳されていて、私たち日本人にもとても読みやすい本を選びました。
どれも心に響く作品ばかりですので、ぜひ楽しんで読んでいただけたら嬉しいです。
アイルランド共和国|『ユリシーズ』/ジェイムズ・ジョイス
「日常の一日が、壮大な冒険になる。」そんな言葉がぴったりの一冊。
『ユリシーズ』は、1904年6月16日、ダブリンの街を舞台にした長編小説です。
主人公ブルームが過ごす一日を描きながら、登場人物の内面や都市の細部が、繊細な文体と“意識の流れ”という手法で綴られています。
この物語は、まるで大阪万博のパビリオンのように、多様な視点や歴史、価値観が交差する世界。ページをめくるごとに、人と人、過去と未来がつながっていく感覚に包まれます。
日常の中に潜む発見、言葉の奥深さ、自分を見つめ直す時間──
そんな読書の旅を求めている方に、おすすめしたい海外文学です。
まずは、気になる章から少しずつ。
あなたの「いつもの日」が、きっと新しい冒険へと変わっていきますよ。
ジェイムズ・ジョイス(1882–1941)はアイルランド・ダブリン生まれの小説家・詩人。『ユリシーズ』『若き芸術家の肖像』などで知られ、20世紀モダニズム文学を代表する存在。「意識の流れ」や神話的手法を駆使し、言語の可能性を追求した革新的な作風で評価されました。
アイルランド共和国|『ゴドーを待ちながら』/サミュエル・ ベケット
「待つこと」に心が揺れる今──そんな時におすすめしたいのが、サミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』です。
一本の木の下で“ゴドー”という存在を待ち続ける二人の男の姿を通して、この物語は、希望と不安、そして人間の普遍的な感情を描き出します。
大阪万博のパビリオンもまた、未来を信じてかたちにする場所。見えない何かを待ちながら過ごす時間は、実はとても大切なものなのかもしれません。
「あなたのゴドーは、今どこにいますか?」そんな問いと向き合いたいときに、そっと開いてほしい一冊です。
サミュエル・ベケット(1906–1989)はアイルランド生まれの劇作家・小説家で、「ゴドーを待ちながら」に代表される不条理演劇の旗手です。戦後はフランス語で執筆し、小説三部作や戯曲で高く評価され、1969年にノーベル文学賞を受賞。晩年までパリで創作活動を続けました。
英国|『高慢と偏見』/ジェーン・オースティン
誤解から始まる恋──自分の“思い込み”に気づいたとき、人生は少しずつ変わり始めるんです。
そんな気づきを、そっと教えてくれる一冊があります。それが、18世紀末のイギリスを舞台に描かれた、ジェイン・オースティンの名作『高慢と偏見』です。
物語の主人公は、快活で知的なエリザベスと、誇り高き資産家ダーシー。
ふたりは最初こそ、お互いに対する偏見や高慢さから何度もすれ違ってしまいます。
でも、少しずつ相手を理解し、自分自身の思い込みに気づいていくことで、心の距離が近づいていくんですね。
そんな「誤解から理解へ」の過程は、大阪万博のパビリオンで体験できる“多様性との出会い”にも重なります。
国や文化、背景の異なる人たちが集い、時に誤解しながらも、歩み寄り、理解し合う。『高慢と偏見』は、まさにそんな“共感と成長”の物語なんです。
人間関係でちょっと悩んでいるとき。
誰かとすれ違った気がするとき。
そんな時にこの海外文学を手に取ると、自分の見方が少しやわらかくなるかもしれません。
大阪万博をきっかけに、本で“世界の見え方”を広げてみませんか?
まずは、気軽に1章だけでも。きっと、あなた自身の中にも新しい発見が待っていますよ。
ジェーン・オースティン(1775年12月16日~1817年7月18日)は、イギリス・ハンプシャー州スティーブントン生まれの小説家です。18~19世紀のイングランド中流社会を舞台に、結婚や女性の私生活を鋭く描き、皮肉と愛情を込めた作品で評価されました。代表作には『分別と多感』『高慢と偏見』『マンスフィールド・パーク』『エマ』などがあります。生涯独身で、家族と穏やかな生活を送りながら創作活動に専念しました。
英国|『二都物語』/チャールズ・ディケンズ
革命の時代を生きた人々の選択が、いまの私たちに問いかける。
「激動の時代に、私たちは何を選ぶのか──」
そんな問いが胸に残る、永遠の名作『二都物語』。
ロンドンとパリ、ふたつの都市を舞台に、フランス革命のうねりの中で交錯する運命と人間ドラマが描かれています。
貴族出身ながら正義を貫こうとするダーニー。
そして、自らを犠牲にしてでも人を愛しぬこうとする弁護士カートン。彼らを結ぶルーシーとのつながりが、物語にあたたかな光を灯します。
この作品が今あらためて注目されるのは、「変革」や「共生」というテーマが、私たちの時代にも深く通じるからかもしれません。
大阪万博のパビリオンでも語られる「多様性」や「未来への希望」と響き合いながら、私たちがどう生き、どんな価値を大切にしていくのか──そんな問いをやさしく投げかけてくれます。
歴史や社会の変化に関心のある方、人とのつながりや生き方を見つめ直したい方には、特におすすめしたい一冊です。
この本には、正義とは何か、自由や友愛とはどうあるべきか──そんな普遍的なテーマが、静かに、そして力強く込められています。
もし今、「何かを信じたい」「誰かとつながりたい」そんな思いを胸に抱えているなら、ぜひ『二都物語』を手に取ってみてください。きっとあなたの心にも、深く響く言葉が見つかるはずです。
チャールズ・ディケンズ(1812-1870)は、ヴィクトリア朝時代を代表するイギリスの小説家です。貧困の中で育ち、幼少期に多くの苦労を重ねました。法律事務所で働きながら独学で学び、新聞記者を経て作家デビュー。『オリバー・ツイスト』『クリスマス・キャロル』『二都物語』など、社会的弱者に寄り添う名作を次々と発表しました。ディケンズは社会問題を鋭く描き、今も世界中で読み継がれています。
アメリカ合衆国|『老人と海』/アーネスト・ヘミングウェイ
くじけそうな時に、そっと背中を押してくれる一冊
「人は壊れることはあっても、負けることはない」
そんな言葉に、そっと背中を押されたことはありませんか?
『老人と海』は、アメリカ文学を代表するヘミングウェイの海外文学作品でありながら、まるで私たちの日常にも寄り添ってくれるような一冊です。
主人公は、キューバの老漁師サンチャゴ。
84日間も魚が釣れず、誰からも見放されながらも、大海原へと漕ぎ出します。
ようやく出会った巨大なカジキマグロと、命を懸けた死闘の末、獲物を仕留めた彼を待っていたのは帰り道でのさらなる試練──それでも、彼は決して諦めることなく、誇りを胸に港へ戻ります。
大阪万博のパビリオンで感じる「未来社会の挑戦」や「人間の可能性」とも響き合うこの物語は、困難な時代を生きる私たちに、あらためて“挑むことの意味”を問いかけてくれます。
何かに挫折したとき、孤独に押しつぶされそうなとき、「自分なんて」と思ってしまう夜に──
この本は、結果よりも挑戦する姿勢そのものに、価値があることをやさしく教えてくれます。
大阪万博をきっかけに、本との出会いでご自身の「挑戦」を見つけてみませんか?
ページをめくる、その一歩からすべてが始まるかもしれません。
アーネスト・ヘミングウェイ(1899-1961)はアメリカの小説家・詩人・ジャーナリストで、第一次世界大戦では赤十字の救急要員として従軍し、その後パリで文筆活動を始めました。『日はまた昇る』『武器よさらば』などの作品で「失われた世代」の代表作家となり、スペイン内戦や第二次世界大戦にも従軍記者として参加。1952年には『老人と海』でピューリッツァー賞、1954年にノーベル文学賞を受賞しました。代表作には『誰がために鐘は鳴る』もあり、晩年は精神的な病に苦しみ、1961年に自ら命を絶ちました。
アメリカ合衆国|『ロング・グッドバイ』/ レイモンド・チャンドラー
「友情と喪失、そして“自分の正しさ”を信じること」
そんなテーマに心を揺さぶられたことはありませんか?
今回ご紹介するのは、アメリカの作家レイモンド・チャンドラーによる海外文学の名作『ロング・グッドバイ』。
主人公の私立探偵マーロウは、謎めいた男・テリーとの友情を通じて、人の裏切りや弱さ、そして信じる力の意味を静かに問いかけてきます。
テリーが残した手紙を手がかりに、マーロウがたどるのは、ただの事件解決ではありません。
それは、人との絆や信頼、自分の信念を貫くことのむずかしさと尊さに向き合う旅でもあるのです。
この物語には、「多様な価値観の共存」や「人間の本質」といった、大阪万博のパビリオンで語られるテーマとも響き合うメッセージが込められています。
人と人とが交差するこの時代、マーロウのように「自分なりの正しさ」を見つめ続ける姿は、どこか私たち自身と重なるのではないでしょうか。
「人との距離感に悩んでいる」「信じることに疲れてしまった」
そんなあなたにこそ、そっと手渡したい一冊です。
大阪万博をきっかけに、少し立ち止まって、自分自身と向き合いたくなった時──この本が、きっとやさしく背中を押してくれますよ。
レイモンド・チャンドラー(1888年7月23日~1959年3月26日)は、アメリカ・シカゴ生まれの小説家・脚本家で、ハードボイルド探偵小説の巨匠です。第一次世界大戦後、アメリカに戻り石油会社勤務を経て作家に転身。1939年に代表作『大いなる眠り』で私立探偵フィリップ・マーロウを登場させ、7作の長編を発表。ハリウッドでは脚本家としても活躍し、アカデミー賞にもノミネートされました。
カナダ|『アンの青春』/ルーシー・モード・モンゴメリ
「夢を持って、自分らしく生きていきたい」──そんな気持ちを抱えているあなたに、そっと寄り添ってくれる海外文学があります。
それが、カナダ文学の名作『アンの青春』。
16歳になったアンが、小学校の先生として奮闘しながら、新しい出会いや別れを経験し、大人の女性へと少しずつ成長していく姿が描かれています。
マリラが引き取った双子の世話や、村をより良くするための仲間たちとの活動を通じて、アンは“自分らしさ”や“人とともに生きること”の大切さを学んでいくのです。
そんな物語は、大阪万博のパビリオンが描く「多様性」や「未来への希望」とも重なって見えてきます。万博では、世界中の文化や価値観に出会いながら、共に生きる喜びや、新しい一歩を踏み出す勇気が育まれますよね。
『アンの青春』もまた、読者の背中をやさしく押してくれる一冊。
失敗や悩みに迷う日も、誰かと歩くことで前を向ける──そんな温かな気づきが、ページをめくるたびに訪れます。
新しい環境に踏み出す方や、友情・家族との絆を大切にしたい方にもぴったりの本です。
大阪万博をきっかけに、本の中でも“未来”と向き合ってみませんか?アンのまっすぐな心にふれたとき、あなたの毎日がきっと、少し明るく変わっていきますよ。
ルーシー・モード・モンゴメリ(1874年11月30日–1942年4月24日)は、カナダ・プリンスエドワード島生まれの小説家です。幼少期に母を亡くし、祖父母に育てられました。教師、郵便局員、新聞記者を経て執筆を続け、1908年に『赤毛のアン』で世界的に有名になります。その後もアン・シリーズやエミリー・シリーズをはじめ、児童文学や詩、日記を数多く執筆し、カナダ文学の重要な作家として名を馳せました。
カナダ|『ジェーンとキツネとわたし』/ファニー ブリット
「自分の居場所がない気がする」「ひとりでいる方が楽」──そんな思いを、ふと抱いたことはありませんか?
今回ご紹介するのは、そんな心にそっと寄り添ってくれる、海外文学のおすすめグラフィック・ノベルです。
主人公のエレーヌは、学校で仲間外れにされ、孤独な日々を過ごしています。そんな彼女の心のよりどころは、愛読書『ジェーン・エア』の世界。
しぶしぶ参加した合宿で出会った少女・ジェラルディーヌや、一匹のキツネとの交流が、彼女に小さな変化と、希望の光をもたらしていきます。
繊細なイラストで描かれるその心の揺れは、読む人の胸にもやさしく染み込んでくるようです。
大阪万博のパビリオンには、世界中から多様な人々が集まります。文化や価値観のちがいにふれながら、自分の「居場所」や「つながり」を探していく──。そんな姿は、エレーヌの物語とどこか重なって見えるかもしれません。
・孤独を感じたことのある方
・友人関係に悩んでいる子どもや大人
・繊細な心の機微を描いた本が好きな方
・グラフィック・ノベルに興味がある方──
どれか一つでも心にふれたなら、この本をぜひ手に取ってみてください。パビリオンをめぐるように、本のページをひらけば、きっと新しい出会いが待っています。
ファニー・ブリットはカナダ出身の作家・翻訳家で、約10作の戯曲と15作以上の翻訳を手がけています。特に英語圏の現代作家の作品を多く翻訳しており、代表作『ジェーンとキツネとわたし』でカナダ総督文学賞を受賞しました。
グラフィック・ノベルという言葉、聞いたことはありますか?
これはアメリカで生まれた表現で、マンガのようにコマ割りで描かれたビジュアルブックのことを指します。
普通のマンガよりも物語が少し長めで、内容もぐっと深く、大人の読者を意識した作品が多いのが特徴。でも、もちろん子ども向けのものもあって、幅広い世代に親しまれています。
文学としての読みごたえや、美術的な美しさも感じられる作品が多く、なかには社会的なテーマにしっかりと向き合っているものも。
本の新しい楽しみ方として、気になる一冊から手に取ってみてはいかがでしょうか?
オーストラリア連邦|『ヴォス』/パトリック・ホワイト
自分の“未知”を探しに行きたいあなたへ
誰にでも、「自分はどこに向かっているのだろう」とふと立ち止まってしまう瞬間があると思います。そんなとき、そっと手に取っていただきたい一冊が、オーストラリア文学の名作『ヴォス』です。
この物語は、19世紀のオーストラリアを舞台に、ドイツ人探検家ヴォスが未踏の大地へと旅立つ長編小説。
社会から少し外れた場所にいる彼は、孤独と向き合いながら「自分とは何か」「未知とは何か」を問い続けていきます。
やがて彼は、ローラという女性と不思議な精神的つながりを結び、人間存在や土地の本質に触れていきます。
この“内なる探究の旅”は、大阪万博のパビリオンが描く「未知への挑戦」や「多様性の受容」と、どこか響き合っているように感じます。
ヴォスのように、知らない世界に飛び込む勇気を持つこと。そこには、文化の違いを越えてつながろうとする姿勢や、未来に向かう希望が静かに描かれています。
「本を通して、自分の居場所を見つけたい」
「孤独と対話しながら、新しい価値観を手にしたい」
そんな方にこそ、おすすめしたい海外文学の一冊です。
大阪万博の熱気とともに、自分の“内なる旅”を始めてみませんか?『ヴォス』は、あなたの心の深くに灯る静かな光になるはずです。
パトリック・ホワイト(1912年–1990年)は、オーストラリアの小説家・劇作家で、ノーベル文学賞を受賞した代表作『ヴォス』や『人間の樹』で知られています。ロンドン生まれ、シドニー育ちで、第二次世界大戦後はオーストラリアに定住。20世紀英語圏文学を代表する作家です。
オーストラリア連邦|『奥のほそ道』/リチャード・フラナガン
「極限の苦しみの中で、人は何を信じ、どう生きるのか──」
そんな深い問いを投げかけてくる海外文学のおすすめ作品が、リチャード・フラナガンの『奥のほそ道』です。
物語の舞台は第二次世界大戦下。
オーストラリア人軍医ドリゴは、日本軍の捕虜となり、「死の鉄道」と呼ばれた過酷な鉄道建設に従事させられます。
飢え、暴力、絶望の中で過ごす日々──。
そんな中、一通の手紙が、彼の人生を大きく揺さぶっていきます。
この一冊には、戦前・戦中・戦後を生き抜いた一人の人間の人生が、12年の歳月をかけて丁寧に描かれています。
そこにあるのは、残酷な現実とともに、人間の尊厳、愛、そして“生きる意味”への静かなまなざしです。
大阪万博のパビリオンでも語られる「共生」や「人間の可能性」というテーマに、どこか深く重なり合うような作品です。
異なる文化や背景を持つ人々が出会い、ときにぶつかりながらも、痛みの中から希望や共感を見出していく──。
そんな姿に、胸がぎゅっとなるかもしれません。
戦争文学に関心がある方はもちろん、今、世界と自分とのつながりを見つめ直したいと思っている方にも、そっとおすすめしたい本です。
もし「人間らしさ」や「生きるとは何か」ということに、少しでも心が動いたなら──ぜひ、この本を手に取ってみてください。
きっと、大阪万博で感じたことと重なって、あなたの中に深く残る一冊になるはずです。
リチャード・フラナガン(1961年生まれ、オーストラリア)は、タスマニア州ロングフォード出身の作家で、歴史学を学んだ後、オックスフォード大学で修士号を取得。代表作には『奥のほそ道』(2013年)があり、2014年のマン・ブッカー賞を受賞しました。映画監督や脚本家としても活動し、社会問題に対する発言も多いフラナガンは、2024年に『Question 7』でバイリー・ギフォード賞を受賞し、英国の主要賞を初めて両方制した作家です。
大阪万博パビリオン×海外文学でおすすめの本を楽しむ
万博で心躍った物語を、すぐに手軽に楽しみたい方へ︕
Kindle UnlimitedやAudibleの活用法をわかりやすくご案内します。
Kindle Unlimitedの使い方・料金・解約方法など、初めての方も安心して始められるよう、登録から解約までをわかりやすく解説しています。
Audible完全マニュアル【2025年版】 耳で読む新しい読書体験を、無料体験期間やメリット、解約手順まで網羅しています。
英語圏の作家たちが描く“希望の物語”を読み終えたあと、
少しだけ寂しさを感じたなら、それもまた万博の記憶が生きている証。
👉 大阪関西万博が終わって寂しい…“万博ロス”を癒す本と次に向かうヒント
まとめ
大阪万博のパビリオンを訪れて感じたこと、それはきっと“世界の声”だったのだと思います。
英語圏の海外文学は、そんな声にそっと耳をすませるためのやさしいガイドブックのような存在です。
本の中で、あの国の空気を、あの人の視点を、もう一度たどってみませんか?
あなたの心に残る「一冊」が、このページから見つかりますように!
ほかの地域の本も気になったら、こちらもどうぞ
「大阪関西万博」の世界のパビリオンを、もっとたくさんの物語で旅してみませんか?
気になる地域から、ぜひのぞいてみてくださいね。
シリーズ全体のおすすめ本まとめはこちら
👉 大阪万博で読みたい本おすすめシリーズガイド|パビリオン×海外文学総まとめ
▶海外文学で心を旅したあとは、物語の舞台を“この大阪”に戻してみませんか?
実はね、大阪という街には、小説でしか出会えない風景と記憶があるんです。
👉 大阪を舞台にした小説まとめ|1970大阪万博から2025まで読み解く街と物語の魅力












