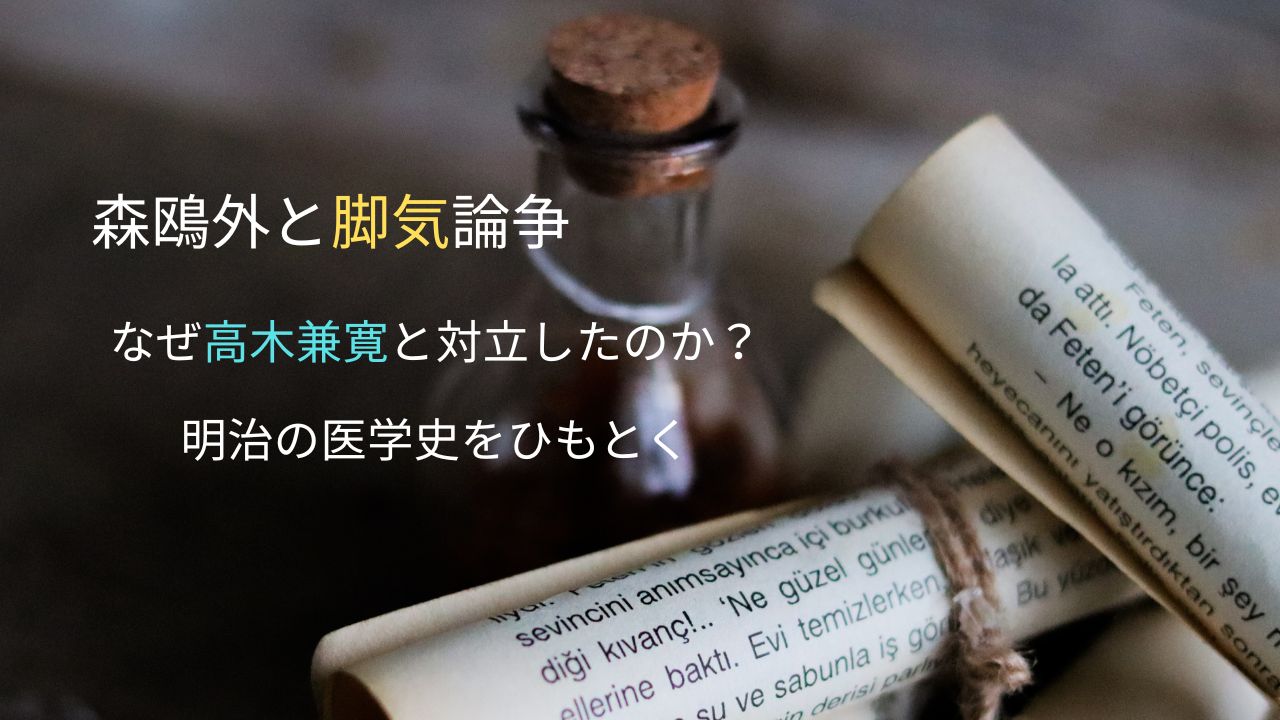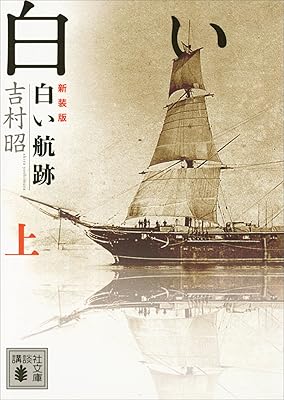「森鴎外は文豪。でも、もとは軍医だったって本当?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
実は森鴎外は、日本の医学史を揺るがす「脚気論争(かっけろんそう)」の中心人物でもあったんです。
森鴎外の名を有名にしたのは文学だけではなく、
“明治という時代の科学と人間のあり方”をめぐる、壮絶な論争でした。
この記事では、森鴎外と高木兼寛(たかぎかねひろ)の対立、
そして脚気という病気を通して見えてくる「知」と「信念」の物語をやさしく解説します。
森鴎外と脚気論争とは?
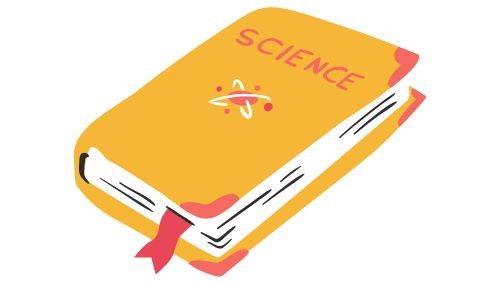
明治時代、日本の陸軍と海軍の間で、脚気(かっけ)の原因と治療法をめぐって激しい議論が起こりました。
それが、のちに「脚気論争」と呼ばれる出来事です。
脚気とはどんな病気?
脚気とは、ビタミンB₁の欠乏によって起こる病気。
手足のしびれやむくみ、倦怠感などを引き起こし、重症化すると心不全に至ることもありました。
しかし、当時はビタミンという概念がまだ知られておらず、
その原因は長いあいだ“謎”だったんです。
明治時代の日本では、白米を主食とする食生活が広まり、軍隊では特に脚気が多発していました。
兵士の命を奪う深刻な問題だったんですよね。
海軍と陸軍で分かれた考え方
当時の海軍では、海上勤務中の兵士にパンや肉、野菜を多く与えた結果、脚気患者が激減しました。
この成果を指揮したのが、海軍軍医・高木兼寛(たかぎ かねひろ)です。
一方、陸軍では「脚気は感染症である」という説が主流。
この立場を取ったのが、陸軍軍医総監だった森鴎外(森林太郎)でした。
つまり、鴎外は“食事説”の高木と、“細菌説”の陸軍の中心に立っていたんです。
なぜ高木兼寛と対立したのか?

森鴎外と高木兼寛の対立は、単なる意見の違いではありませんでした。
そこには、時代の背景や組織の権威、そして「科学とは何か」という深い問いがあったんです。
森鴎外の立場──「科学的根拠を欠くものは信じない」
森鴎外は、ドイツに留学して最新の医学を学んでいました。
そのため、実験や論文など科学的な証拠(エビデンス)を重視したんです。
当時の陸軍では細菌学が最先端の学問であり、
「脚気は感染症ではない」とする証拠が乏しい高木の説を認めにくかったのでしょう。
森鴎外の考えは今でいう“エビデンス主義”に近く、科学的厳密さを守ろうとする姿勢だったんですよね。
高木兼寛の立場──「人の命を救うことが先だ」
一方、高木兼寛はイギリスで公衆衛生を学び、
「病気の原因が何であれ、まず結果を見よ」と考えていました。
食生活を改善すれば脚気が減る──
その“現場での成果”こそが真実だと信じていたんです。
つまり、鴎外が「理論」で立ち向かったのに対し、
高木は「実践」で闘ったと言えます。
まさに、理性と現場のぶつかり合いだったんですよね。
陸軍の失策と論争の行方
結果として、陸軍では脚気による死者が相次ぎました。
1904年の日露戦争では、脚気による死者が戦死者を上回るという悲劇も。
森鴎外はこの現実を前に、
次第に「理論の正しさ」よりも「人の命」を考えるようになっていったといわれています。
最終的には、ビタミンB₁の発見によって「食事説」が正しいと証明されました。
しかし森鴎外は、最後まで自らの立場を明確に否定しなかったんです。
そこには「科学とは常に検証されるものだ」という彼の哲学があったのでしょう。
明治の医学史から見えるもの

この脚気論争は、単なる医学の歴史ではなく、「明治という時代の思想」そのものを映し出しています。
理性と情熱──鴎外の“人間らしさ”
森鴎外は、理屈っぽい頑固者だと語られることもありますが、
本当は“人の命に真剣だった人”なんです。
ただ、森鴎外にとってそれは「感情」ではなく、「知への誠実さ」だったんですよね。
理性で世界を理解しようとした鴎外と、
情熱で人を救おうとした高木。
この2人の姿勢は、今の医療や科学にも通じるテーマを投げかけています。
失敗ではなく、挑戦の記録
「森鴎外=脚気論争で間違えた人」と思われがちですが、
本当はそうではありません。
当時の日本に“ビタミン”という概念がなかった以上、
誰もが手探りで真実を求めていたんです。
森鴎外の論争は、「科学の限界をどう受け止めるか」という問いを、
私たちに残してくれた貴重な記録なんです。
📚医師としての鴎外を知ると、彼がどれほど真剣に「理性と倫理」を見つめていたかが伝わってきます。
文学と科学、その両面から鴎外という人を見てみたい方は、こちらの記事へ。
👉 森鴎外とはどんな人?生涯・代表作・人物像から見る明治の文豪の全貌
森鴎外と脚気論争を知るおすすめ書籍
もしこのテーマをもう少し深く知りたいなら、以下の本がおすすめです。
脚気をなくした男 高木兼寛伝/松田誠
明治の日本で、命を救うために立ち上がった一人の医師がいました。
『脚気をなくした男 高木兼寛伝』(松田誠/講談社)は、脚気という“見えない敵”と闘い、人を診る医学を貫いた高木兼寛の生涯を描いたノンフィクションです。
白米中心の食事が命を奪っていた時代に、彼は麦飯をすすめ、実験と実践で命を守りました。
しかし、その信念は当時の医学界に受け入れられず、孤独な闘いを強いられます。
この本を読むことで、「正しいことを貫く勇気」や「人のために学ぶ意味」が静かに胸に刻まれるんです。
科学の物語としても、人間ドラマとしても、深く心を打つ一冊です。
病気を診ずして病人を診よ/倉迫一朝
倉迫一朝『病気を診ずして病人を診よ―麦飯男爵・高木兼寛の生涯』は、「病気を見るな、人を見よ」という信念を貫いた医師・高木兼寛の生涯を描いた評伝です。
宮崎の小村から英国へ渡り、海軍の脚気を麦飯で救い、慈恵医大を創設──その歩みは、まさに“命と向き合う医療”の原点なんです。
ただの伝記ではなく、「なぜ彼はここまで人に尽くせたのか」を丁寧にたどる一冊。
現代医療や看護、福祉の仕事に携わる方にも、心を支える指針が見つかります。
データではなく、思いやりで人を救う――その志に、読む人の胸が静かに温まる本です。
脚気論争を人間的・倫理的側面から読み解きたい人に最適の一冊です。
白い航跡/吉村昭
明治という激動の時代に、ただ一人、真実の医療を信じ抜いた男がいました。
吉村昭『白い航跡(上・下)』(講談社文庫)は、東京慈恵会医科大学の創立者・高木兼寛の生涯を描いた感動の長篇小説です。
戦乱の中で漢方医学の限界を知り、遠く英国に渡って西洋医学を学んだ高木兼寛。
帰国後は、脚気に苦しむ兵士たちを救うために、命を削るように研究を続けます。
権威に屈せず、ただ「人を救いたい」という信念だけで進んだその姿は、読む人の心に静かに火を灯すんです。
史実に基づいた重厚な物語でありながら、読むたびに「信念とは何か」「正しさを貫くとはどういうことか」を問い返してくれる一冊。
困難に向き合うすべての人に、勇気と確信を与えてくれる本です。
いずれも、明治の科学者たちの葛藤を丁寧に描いています。
電子書籍で読みたい方は、
👉 Amazon Kindle Unlimited|料金・解約・使い方まとめ
から検索してみてくださいね。
また、耳で聴きながら理解を深めたい方は
👉 Amazonオーディブル完全マニュアル|無料体験期間・メリット・解約手順
もおすすめです。
家事の合間に聴くだけでも、明治のドラマがすっと入ってきますよ。
まとめ|理性と信念のあいだで揺れた“もう一人の鴎外”
森鴎外と高木兼寛の脚気論争は、
「どちらが正しかったか」よりも、
「どう生きたか」を私たちに問いかけているようです。
科学の進歩も、人の命も、どちらも大切。
その間で迷いながらも、誠実に答えを探し続けた森鴎外の姿は、
今を生きる私たちにも響くものがありますよね。
この機会に、文豪・鴎外ではなく“軍医・森林太郎”の姿を本や朗読で味わってみませんか?
きっと新しい一面に出会えるはずです。