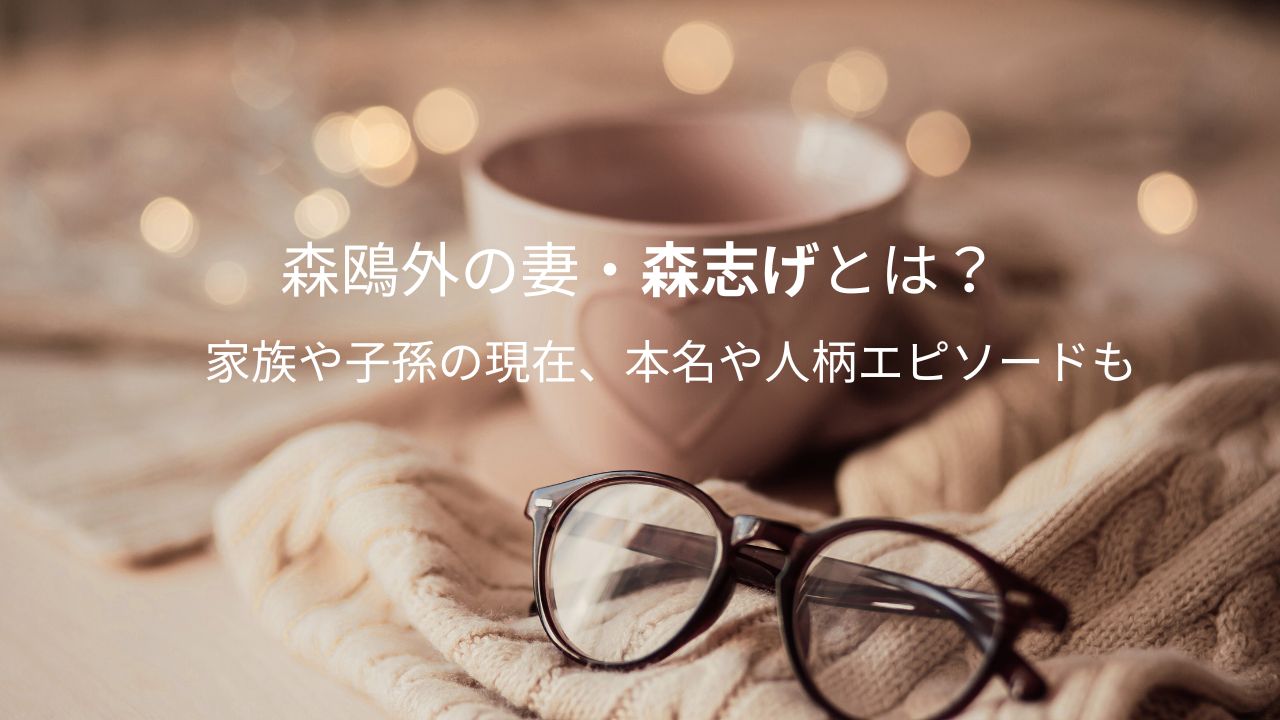明治を代表する文豪・森鴎外(もり おうがい)。
名前はよく聞くけれど、「どんな人だったの?」「妻や家族はどんな暮らしをしていたの?」と感じたことはありませんか?
この記事では、森鴎外の妻・森志げ(しげ)の人物像を中心に、
家族や子孫、本名「森林太郎(もりりんたろう)」としての素顔までをやさしく解説します。
文学の裏にあった“家庭人としての鴎外”を知ると、彼の作品がぐっと身近に感じられるはずです。
森鴎外の妻・森志げとは?

森鴎外の妻・森志げ(もり しげ)は、1880年(明治13年)に東京で生まれました。
実家は旧士族の家柄で、品があり、教養も身につけた女性だったと伝えられています。
結婚したのは1893年(明治26年)、鴎外が31歳、志げがまだ13歳の時。
当時は珍しくなかったとはいえ、大きな年齢差婚でした。
結婚後、志げは東京・千駄木町(現在の文京区)で暮らし、4人の子どもをもうけます。
夫・森鴎外が軍医総監として多忙な日々を送るなか、家庭を静かに支え続けた女性でした。
気丈で穏やかな性格だったと言われていますが、その芯の強さが森鴎外にとっての安らぎだったのかもしれませんね。
森志げの性格と、森鴎外が信頼した理由
森志げは、表に出ることを好まない控えめな女性でした。
しかし、家庭を守る姿勢は一貫していて、森鴎外もその誠実さに深い信頼を寄せていたといわれています。
当時、文豪たちの妻は「夫の影」として生きるのが当たり前の時代。
それでも志げは、家族の中であたたかな空気を生み出していたようです。
晩年の森鴎外が病床で「志げがいるから安心だ」と語ったという逸話は、
この夫婦の静かな絆を象徴しているように感じます。
森鴎外と子どもたちとの関係
森志げと鴎外の間には、4人の子どもが生まれました。
長男・森於菟(おと)は医師として東京大学の教授となり、父の医学の道を継ぎます。
長女・杏奴(あんぬ)はエッセイストとなり、父の記録を世に残しました。
次女・茉莉(まり)は作家として知られ、フランス文学の香りを感じさせる繊細な作品を数多く発表。
四男・類(るい)は建築家を志し、芸術的な感性を受け継ぎました。
このように、森家は“知と芸術の家系”として今も語り継がれています。
家庭の中に文化の香りがあったことは、母・志げの静かな支えがあってこそだったのではないでしょうか。
森志げの晩年
森鴎外が1919年(大正8年)に亡くなったあとも、志げは静かに暮らしを守り続けました。
夫の死後、彼女は家族の記録や遺品を大切に保管し、鴎外の文学的遺産が後世に伝わるよう努めたといわれています。
彼女自身は表舞台に立つことはありませんでしたが、その誠実な姿勢は「森家の良心」として記憶されています。
家族や子孫の現在、本名や人柄エピソードも
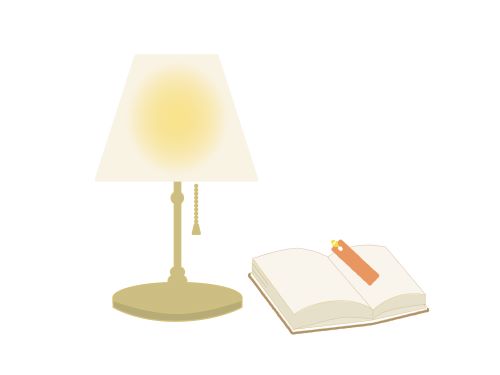
ここからは、本名「森林太郎」としての森鴎外の人生と、家族とのあたたかな関係を見ていきましょう。
森鴎外の本名と生い立ち
森鴎外の本名は森林太郎(もりりんたろう)。
1862年(文久2年)、島根県津和野の旧藩医の家に生まれました。
幼い頃から神童と呼ばれ、11歳で上京。15歳で東京大学医学部に入学という、まさに“天才少年”だったんです。
彼は軍医として日本の衛生学の発展に貢献し、明治政府に重用されました。
しかし、ドイツ留学を経て帰国後、彼の興味は次第に「人間の内面」へと移っていきます。
理性の象徴・医師と、感情の象徴・文学者。その二つを併せ持つ人物でした。
「鴎外」という名前に込められた想い
「鴎外」という筆名は、海を自由に飛ぶ“かもめ(鴎)”から取ったといわれます。
当時、社会や体制の中で生きることの窮屈さを感じていた森鴎外にとって、
この名は「自由に思想を羽ばたかせたい」という願いそのものだったのかもしれません。
ちなみに、留学中には「オルガニズム(有機体)」という言葉に魅せられた時期もあり、
生きることそのものへの洞察を深めていったそうです。
筆名にも、そんな“生命観”が滲んでいるように思いますね。
森鴎外が家庭で見せた優しい素顔
軍医総監という厳しい立場にありながら、家庭ではとても温かい父親でした。
子どもたちを抱き上げて笑ったり、時には自分で料理をふるまったり。
娘・杏奴の日記には「父はよく本を読んでくれた」との記述も残っています。
厳格なイメージのある鴎外ですが、
その内側には、家族を想うやさしさと、子どもたちに文学の楽しさを伝えたいという想いがあったんですよね。
森鴎外のエピソードで知る人柄
鴎外は後進の育成にも熱心で、若い文学者を自宅に招き、よく語り合いました。
弟子の中には、のちに文壇で名を残す人も多く、
「人を育てる」ことにも情熱を注いでいたんです。
また、軍医としての冷静さと、文学者としての感受性。
その二面性があるからこそ、『舞姫』のような“理性と情熱の葛藤”を描けたのかもしれませんね。
森鴎外の子孫と現在
森鴎外の曾孫にあたる森まゆみさんは、現在も作家・編集者として活躍しています。
「谷中・根津・千駄木(谷根千)」の街歩き文化を広め、
地域の記憶を文学として残す活動を続けています。
こうして見ると、森家は今も“言葉で人をつなぐ家族”なんですよね。
森鴎外の精神は、時代を超えて息づいているようです。
家族の物語を知ると、鴎外の作品の奥に流れる“人間らしい温度”が感じられます。
もし「鴎外という人そのもの」をもっと知りたくなったら、こちらをのぞいてみてくださいね。
👉 森鴎外とはどんな人?生涯・代表作・人物像から見る明治の文豪の全貌
森鴎外の作品を読むなら
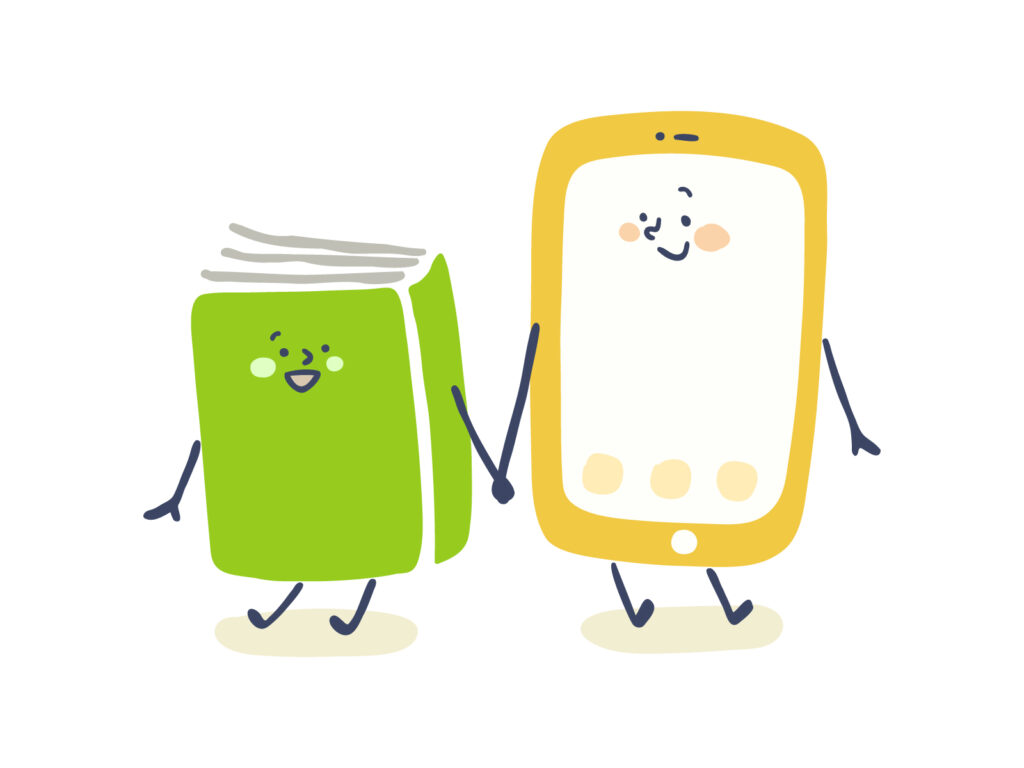
もし、森鴎外の人柄をもっと感じてみたいなら、
短編『高瀬舟』や『山椒大夫』を読んでみてください。
そこには「生きるとは何か」「人を赦すとはどういうことか」という深いテーマが流れています。
電子書籍で手軽に読むなら
👉 Amazon Kindle Unlimited|料金・解約・使い方まとめ
で対象作品をチェック。
また、朗読で味わいたい方には
👉 Amazonオーディブル完全マニュアル|無料体験期間・メリット・解約手順
がおすすめです。
耳で聴く鴎外文学は、まるで静かな詩のように心に染みてきます。
まとめ|妻・森志げが支えた“静かな愛のかたち”
森鴎外は「理性の人」でありながら、「愛の人」でもありました。
妻・志げの存在は、彼の人生を穏やかに支え続けた“見えない灯”のようなもの。
文学の裏には、家族を想い、人生をまっすぐに生きたひとりの人間がいました。
この機会に、彼の作品を通して“家庭人としての森鴎外”を感じてみませんか?
きっと、あなたの中にも静かな温もりが広がるはずです。